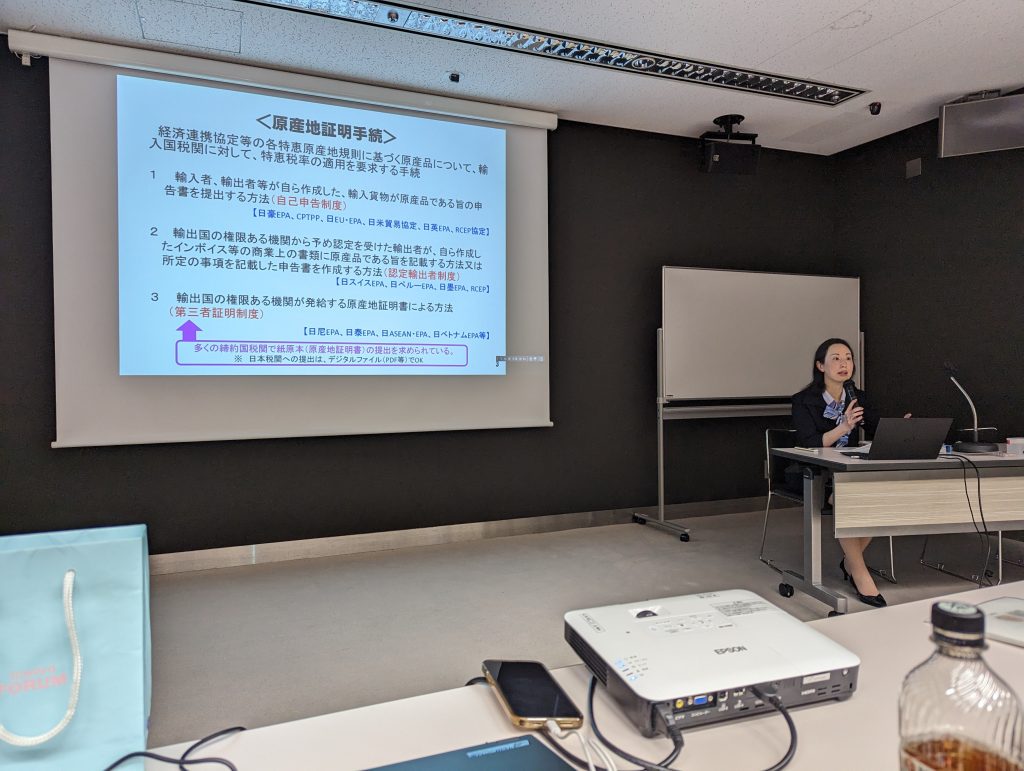第三者証明では、日本商工会議所に原産地判定を申請して承認が得られないと特恵原産地証明書の発給を受けることが出来ません。
それ故に、原産地証明の証拠書類が出来ると、日本商工会議所(実際は8つの商工会議所事務所から1つを選択)に証拠書類を提出し判定依頼を依頼します。
困るのは、そこで商工会議所から指摘されることが的を得ていない場合があること。
当社は企業に代り、原産地証明を行い、商工会議所に判定依頼をし、やりとりをして判定を受けるまでを代行業として行うことをしています。
FTAのコンサルティングと称して、原産判定までを具体的にやったことのない企業は信用できませんからね。理屈だけの企業が残念ながら存在するのは業界として困ったものです。当社は原産の判定を行う全ての商工会議所とのやりとりを経験しています。彼らの指摘ももっともだと思うところは、当然反映し、今後の代行業での糧としています。
今回は日インドCEPAの活用だったのですが、一般規則の適用品でCTCとVAを用意しなければなりません。ご存じの通り、CTCとVAでは対象となる部材表が違います。それに従って証明せねばなりません。
当社が提出した商工会議所からの指摘事項には納得がいきませんでした。いくつかあります(多くはこの場では伏せます)が、一番びっくりしたのはCTCの対比対象外の部材にもHSコードを付番せよとのこと。今までにも多くのインド向けの証明をしてきましたが、このような指摘は初めてです。
当方が指摘に対して主張をして、先方が当方の主張に対し、日本商工会議所国際部と打ち合せをした上で再び戻ってこられた回答は、HSコードの付番は必要ないが、表記はこうしてほしいということ。そこで戦っても仕方ないので、追加の表記は了承し、原産判定が下りました。
商工会議所の指摘事項は、「こうしなさい」と来るので、「通常の企業の人はそれに従うんだろうな。」と思うことが割とあります。(彼らの名誉のために申せば、なるほどと思うことも多くあります)
民間コンサルタントの私と、商工会議所の見解と企業はどちらをまず信じるかと言えば後者ですよね。それ故に、「おかしい」との文句が当社に来ます。当方は本当に困るのです。当方の間違いなら致し方ないのですが、多くを経験しているので、「この指摘、おかしい」と思うことがしばしあるのです。
今回の件の1つの事例、対象外の部材に対してHSコードを付番することは労力がとてもかかります。はっきり言って不必要です。指導される方は多くの案件をかかえてらっしゃるのでしょうが、もう少し勉強されたらと思います。また、商工会議所間での認識のギャップはいまだ解決されておらず、Aの商工会議所ではOKだったものが、Bではだめというものがあります。
商工会議所からの原産地証明の指摘事項、ありがたいことではありますが、当方もよく学んだ上で、指摘を咀嚼して、不必要なものは不必要と言えるようにならねばなりません。